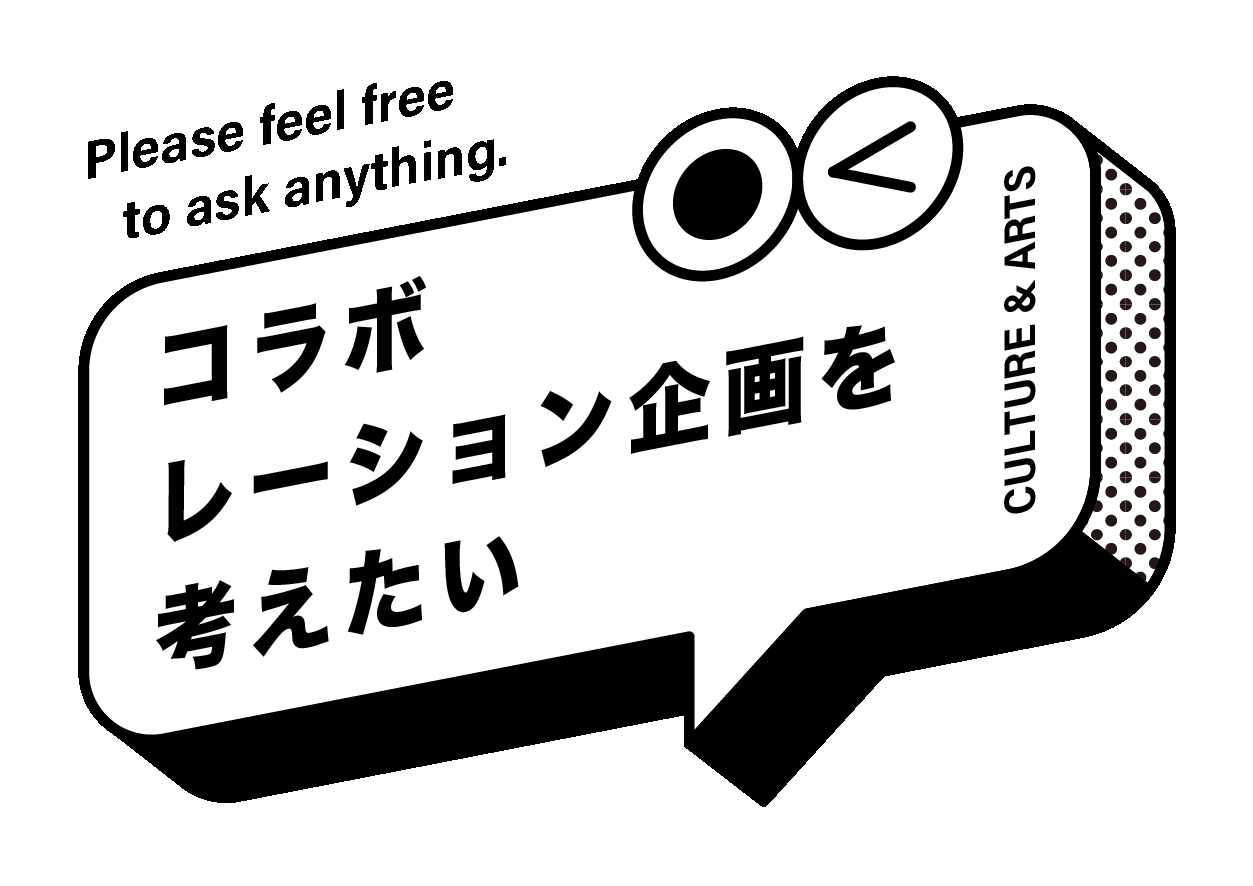top of page

BLOG


金孝妍展|線ヲ思フ|天プラ・セレクションVol.79
絵を描くのがただ好きだった。 ある時、ふと、線を一本描くことに虚飾な感じがし、描けなくなった。 ここから自分への問いは始まる。 なぜ、絵を描くのか。 絵画とは。アートとは。 次々とつながる問いは作品を生む種となる。 自分への問いは、自分の行為に対する問いに繋がる。...


杉山恭平展|空想の世界|天プラ・セレクションVol.78
展示を振り返って いずれはと思いつつも、地元岡山県での作品展示(個展)はなかなか難しく、今回この様な形で地元にて作品展示をさせて頂ける機会に恵まれた事は、本当に有難く喜ばしい事でありました。 私は作品作りにおいて、複雑なコセンプトや機微は一切持たせず、「老若男女国籍問わず、...


髙原洋一 展|反復:生成|天プラ・セレクションVol.77
反復はレピート、繰り返しである。服地のプリント模様や壁紙には図柄の継ぎ目が見えないよう巧妙にレピートされている。「KIBI KOMON」(吉備小紋)と名づけられた作品は小さな点描の繰返しを用いて大きな画面に仕上げている。異なる版を組み合わせることによって視覚的なイリュージョ...


安中 仁美 展|ささやかな備忘録|天プラ・セレクションVol.76
普段目にしているはずのモノや風景も、ふとした瞬間琴線に触れることがあります。 何がいつもと違うのだろうという疑問が興味へとつながります。―「何か気になる。」 私の場合、創作のインスピレーションが沸くのはこんな時です。 そして作品づくりに取り組む際には、次のことを考えるように...


有松啓介ガラス作品展|ガラスでしりとり遊び|天プラ・セレクションVol.75
「しりとり」をガラスで表現するというアイデアは数年前から持っていました。 しかし実現するためには当然、いろいろなものを作るという覚悟と冒険心が必要です。 そのため普段の展示会ではなかなか実現できませんでした。 それを、今回の天神山文化プラザの個展で、とうとう「試みてみようか...


妹尾 佑介 展|VIVID!|天プラ・セレクションVol.74
会期初日、小学生くらいの子供たちが会場にきて、 長い時間、不思議そうに絵を眺めていた。 最近、創造へのモチベーションの根源は、 他者の心に干渉したいという欲求ではないかと、ふと思った。 今回の展覧会は、どれほどの人の心に干渉できただろう。 私の絵は、日常の中の、ささやかな、...


藤井 龍 展|For( Your/His/Her/My)Eyes Only|天プラ・セレクションVol.73
名づけられなかったことについて たわいもない会話、それをパフォーマンスだと名づける。ほとんど反射的におこなっているようなやりとりの内容や、やりとり自体が意味ありげなものに見えてくる。 自宅で忘れられたように飾られている絵画。日々の生活の中でほとんど鑑賞されなくなり、日常の背...


眞嶋 青 展|museum|天プラ・セレクションVol.72
私は自分の作品を語るうえで、「表現」という言葉を使うことに違和感を覚える。 元々自分を表現することが苦手な私にとって、作品の中に自分の思想や感情を込めるのはとても難しいことである。 私が目指すのは、自分の痕跡ができるだけ存在しない作品である。...


島田悠美子展|増殖する記憶 ―目に見えない生命のかたち―|天プラ・セレクションVol.71
はてしない時間の中で静かに増殖する“いのち”。 ミクロの世界を覗いてみると、 一つ一つの小さな細胞が規則的な配列で集合している様子は、 それらがまるで記憶や意思を持って成長している美しい情景のようであり、 その秩序ある複雑で美しい幾何学パターンに自然の驚異を感じます。...


山本哲也展|袖は襟で襟はなくないものはある|天プラ・セレクションVol.70
僕の好きなファッションは、不思議なものでうまく言葉にできない。 服を作るときには着る人のことや着たときのことを考える。 あるいは、ときどき全く考えない。 どんなものでも着てみることで気持ちに変化が訪れる。 それは今まで知っていた気持ちや全く知らない何か。...


細見博子展|蝿女|天プラ・セレクションVol.69
輪廻を、謳いたい。 リインカーネーション。 迷いを抜けて、また生と死がめぐる、まわり、まわり。 こたえは、どこに? ― 日々に。 朝と夜と朝と夜と朝と夜と…生活の中での、気づきの瞬間。 耳を澄ませば。澄ますことが出来たなら、色んなことを日々全身で感じることがきっと出来る。...


吉行鮎子展|エモーションが止まらない|天プラ・セレクションVol.68
目に見えるものだけが真実ではない。 見えている部分はわずかで、 水面下には何倍にも及ぶ巨大な氷塊が沈んでいる。 感情の爆発も、 地球温暖化の影響も、 じわりじわりとやってくる。 ある日、 積み重なったものが突如に崩れる。 雪崩のように。 吉行 鮎子...


丸山智代展|私の秘密の住人たち|天プラ・セレクションVol.67
銅版画の魅力は、まるで錬金術師のように、色々な道具を使い、長い時間をかけて、ただの銅の板を「版」に変えていく工程にあると思う。直接ビュランで彫ったり、針で傷をつけたり、または酸で腐蝕させたりしながら描き、刷り上がりをイメージしながら製版する。プレス機で紙にインクで絵は印刷さ...


カスパー・シュワーベ展|ars geometrica|天プラ・セレクションVol.66
"ARS GEOMETRICA" means the art to measure the earth(Geo). This includes mountains and seas, plants and animal and human life. The...


三宅良史展|日本画×インスタレーション|天プラ・セレクションVol.65
天神山文化プラザ、記憶が曖味ですが高校美術展の様な催しで展示した記憶が有ります。それが確かなら凡そ30年ぶりとなります。東京から地元に戻って12年経ちますが、存在すら忘れて打ち合わせの為に訪れた際に懐かしさがあったのはその所為かもしれません。よくぞ残っていてくれました。この...


片山康之展|完成形の可塑性能|天プラ・セレクションVol.64
「労の集積」 私は具体的なモノとして美術的に可視化された「かたち」をみせる作家だ。 空間の演出家ではないし、意味やストーリーをみせるタイプでもない。 その前提において本展は、展示構成と空間の作り込みが本来すべき事の隠れ蓑になっているように思えた。...


宮崎政史展|天プラ・セレクションVol.63
作品は、自分にとって、日付の無い日記みたいなものだと思っています。 それらを、完成した直後のように、今思っている事のように、 新鮮さを失わさせずに展示したいと思いました。 いつだって、大事な事や思っている事は変わらないのに、 見失ってしまう時があります。...


真部剛一展|虚実皮膜|天プラ・セレクションVol.62
私は今までに中国の黄土高原に住む方々、ジモトに住むホームレス、障害のある方、瀬戸内海の島に住む高齢の方、在日コリアンの方々と長期的に関わらせていただきました。本展覧会では、その関わりのなかから見出された問題を、ワークインプログレスの作品として発表いたしました。...


胡桃澤千晶展|かげろうエレジー|天プラ・セレクションVol.61
2011年の東北の震災、大津波から4年が経ちました。 水をテーマに制作活動してきた私にとって、 今まで携わってきた水とは違う別の一面と向き合うことになりました。 地上の生命を育む一方で、全てを奪う存在にもなり得る水。 古来より人は、その力に畏敬の念を抱きながら水と共に暮らし...


加藤晋平 写真展|家族のカタチ2|天プラ・セレクションVol.60
2011年、僕は震災・原発事故をきっかけに家族4人で岡山へ移住した。その後、同じように多くの人が岡山に移ってきたことを知る。 彼らの中には、そのまま定住する人もいれば、また別の土地へ移って行く人もいた。以前住んでいた場所に戻った人も少なくない。僕は、そんな“移ろい”の中にあ...


藤原裕策展|ゴルゴダ ―展翅のささやき―|天プラ・セレクションVol.59
細胞のDNAに記録された遺伝情報は、複製されて子孫に伝えられ、生物は進化してきました。DNAの複製では、ほんのわずかな違いが万人に日々生じているそうです。もしDNA複製がコンピューターのように確実に繰り返されていれば、個性は生まれず、生物の多様化も起こらなかったのかもしれま...


鳥越 眞生也 作品展|あにまるまにあ|天プラ・セレクションVol.58
本展示作品中の動物をモチーフとした連続模様は、1種類(又は2種類)の形で隙間なく平面を埋め尽くします。個々の形は、隣に接した形と輪郭線を共有しており、ひとつひとつの形が、ある時は「図」に、またある時は別の形の背景として「地」となり、同じ形であるのに、視線を移す度にその役割を...


榎 真弓 展|それらのあいだにも。|天プラ・セレクションVol.57
本日々の営みとしての作品たちを、 みなさまに見ていただく機会をもちました。 ただ散らばっている断片が、たまたまに一瞬かさなりあう。 それらのあいだにも、浮かんだり沈んだりしながら。 すぐにひとまとめにすると、わかったような気がするけれど、 溶けあうまで、そのまま待ってみる。...


中山 秀一 展|記憶のレイヤード|天プラ・セレクションVol.56
今回の天プラ・セレクションにおいては、第3展示室・中二階展示室・第4展示室の一連の空間の「見立て」からはじまりました。 普段、海岸で制作を行うことの多い私は、中二階展示室を小高い「岬」とし、眼下に広がる第3展示室にいつもの見慣れた海岸を、第4展示室に現代の都市を想定しました...
bottom of page